〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-509-42
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
Ⅰ 「社会保険労務士の選び方」総合案内
私は、労務管理がやりたくて起業したのではない!
そりゃそうですよね。
ならば、貴方は、社会保険労務士に何を期待しますか?
まずそれを整理してみましょう。
<社労士に期待すること、できること>
起業家のあなたが社労士に期待すること、それは次のような事ではないでしょうか。
① 気軽に労務管理や労働・社会保険に関する相談に乗って欲しい。
② 面倒な労務管理や労働・社会保険の手続きを代行して欲しい。
③ 労働時間の集計や給与計算を代行して欲しい。
④ 助成金の相談や申請手続きの代行をして欲しい。
⑤ 就業規則等規則の作成・変更をして欲しい。
⑥ 人事評価制度、賃金制度などを設計(作成)して欲しい。
⑦ うつ病、過労死など高難度業務への対応を指導して欲しい。
このうち、①〜③の業務は、日常的に所要が発生しますね。
このように日常的に生起する業務を継続的に委託する場合は顧問契約が便利です。
一方、④〜⑦の業務のように、単発的に発生する業務を委託する場合は、通例スポット契約を締結します。ただし、顧問契約を締結している社労士とスポット契約を結ぶのがベターです。
以下、顧問契約とスポット契約に分けて、社労士の選びの視点について考察してみました。
あくまでも私見であることをお断りしておきます。
| 「社会保険労務士の選び方」総合案内(目 次) |
| Ⅰ 「社会保険労務士の選び方」総合案内(Top) |
| Ⅱ 「顧問社労士」の選び方 |
| Ⅲ 「助成金代行社労士」の選び方 |
| Ⅳ 「就業規則を依頼する社労士」の選び方 |
| Ⅴ 「社労士の専門性」について |
Ⅱ 顧問社労士の選び方
顧問契約 ってどんな契約ですか?
顧問社労士はなぜ必要ですか?
顧問契約にはどんな種類がありますか?
顧問社労士選任の視点には、どのような
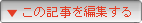
ものがありますか?
このページでは、このような問題を考えてみます。
1 顧問契約とは
「約束(約定)した業務を、通常、月を単位として継続的に契約・サポートすること」を言います。
従って、顧問契約により提供されるサービスがあらかじめ固定的に決まっているわけではありません。
「労務管理等や労働・社会保険に関する相談のみ」……相談顧問
「労務管理等や労働・社会保険に関する相談と手続き」……総合顧問
「労務管理等や労働・社会保険に関する相談と手続き+給与計算」……お任せ顧問
という風にいろんなパターンがあります。
2 何故顧問社労士が必要か?
多くの事業主は、労務管理をやりたくて会社を経営している訳ではありません!
そればかりか、ほとんどの事業主様は労務管理、賃金、労働・社会保険についてはずぶの素人と申し上げても過言ではないと思われます。
それでも従業員を雇う以上、「労務管理や社会保険については何にも知らない。どうでもいいや。」というわけには参りません。
かと言って、小さな会社では、高い賃金を支払って労務管理の専門家を1人雇うという訳にも参りません。
ならば、少なくとも労働問題や労働・社会保険についてアドバイスし、あるいは手続きの代行等をしてくれる助っ人が必要です。
この要請に応えてくれるのが顧問社労士です。
真に事業主を思う社労士なら、助成金の申請も請け負ってくれるでしょう。
3 各種の顧問契約
記述のとおり、顧問契約には色々な形がありますが、代表的なものを取り上げてみました。
なお、ここで使用する相談顧問、総合顧問、お任せ顧問等の名称は筆者流の区分・呼称であり、オーソライズされたものではないことをお断りしておきます。
① 相談顧問(相談のみ)
・ 相談顧問とは、労務管理や労働・社会保険について、相談に乗ってくれる顧問社労士
換言すれば、“質問したら答えてくれるあるいはアドバイスしてくれる”社労士です。
・ 小さな会社も、これで必要最小限の労務管理態勢を確立することができます。
・ 「質問 → 回答・アドバイス」という関係では、中々社労士と濃密な関係を築くことは難しく、限定的なサービスにとどまる場合が多いので、余裕ができたら「総合顧問」や「お任せ顧問」を目指したいものです。
② 総合顧問(相談+手続き)
・ 相談に加えて、労務管理や労働・社会保険に関する手続き業務を代行してくれる顧問社労士
※ 標準的な顧問契約です。一般に顧問契約といえばこれを指すことが多い。
・ 手続き業務まで委託するので、顧問社労士とは日頃から接する機会が多くなり、濃密な関係を築くことができます。濃密な関係を築けば、社労士は貴社の状況をかなり詳細に把握することができるので、密接な支援(高度なサービス)を受けることができるようになります。
・ しかしながら、まだ労働時間(勤怠)の管理や賃金計算についてまでは、委託していないので社労士の理解が及びません。すなわち、欠落部分があります。
③ お任せ顧問(相談+手続き+給与計算)
・ 相談・手続きに加えて労働時間の集計や給与計算の代行まで委託する顧問社労士
・ 相談、手続きに加えて、労働時間の集計や給与計算まで代行するので、社労士は顧問先の労務管理の状況をかなり十分なまでに把握することができます。
※ 労働時間や賃金管理まで関与してもらえれば、本当に充実したサポートがを提供することができます。なぜなら、
・ 顧問先の従業員の勤怠、労働時間、賃金体系を確実に把握できる。
・ 規則や通達に基づく適正な労働時間の集計、正しい賃金計算、法定帳簿の整備が抜かりなくできる。
4 顧問社労士選びの視点
① 広く労働問題全般の専門家であること
・ 「就業規則は得意だが、労働時間や賃金に関する指導はできない」などという人では困ります。労働問題を幅広く扱う社労士であること。
※ 社労士には大きく分けて、“労働問題を専門とする社労士”と“年金を専門とする社労士”がいます。勿論、両方をやる社労士もいます。
この内、事業主が求める社労士は、やはり労働問題を専門とする社労士です。
労働問題を専門とする社労士も企業に必要な労働・社会保険に関する知識は備えています。誤解のないようにしてください。
② 経営者が重要と考える分野を得意とする社労士
・ 労使トラブルに強い人、就業規則の作成を得意とする人、人事や労務問題に関するコンサルティングを得意とする人など、意中の人を探してください。
・ 直ちに適任かどうかの見極めがつかないときは、仮契約期間や試行期間を設けるのも一案です。
・ 世の中には、自分に合う人・合わない人、能力の高い人・低い人がいるので注意が必要。
※ 特に報酬の高い・安いのみを判断基準にしないでください。
③ 自分の要求する全分野をカバーできる社労士
・ 賃金計算、助成金の申請、人事制度・賃金制度の設計なども頼みたい方は、それもできる人を選ぶことが重要です。
※1 賃金計算、助成金、人事・賃金制度の設計等をやらない社労士も多いので注意が必要です。
※2 いろんな社労士とスポット契約を結ぶという手もあると思いますが、先ずは労働問題全体をカバーする社労士と顧問契約を締結し、特別の問題が生じたときにその特定の分野に強い人とスポット契約を結ぶというのが正しいやり方です。
Ⅲ 助成金代行社労士の選び方
1 助成金社労士の現況
ものの本によれば、本気で助成金をやる社労士は極めて少ないと言われています。
ところが、社労士のホームページを見てみますと、多くの場合、助成金の代行手数料が掲載されています。
つまり、「やるにはやるが、積極的にはやらない。」ということでしょうか。
なぜ、積極的にやらないのか。
それは「助成金は割に合わない」考える社労士が多いからです。
一方、「たかが書類を作成して提出するだけで、受給した助成金の額の20%〜30%もの報酬を要求するのはいかがなものか?」と考える事業主様が多いのも事実です。
要するに、「助成金の申請代行とは何か?」ということが、理解されていないようです。
細部は、下記URLをご確認ください。
2 助成金申請代行の業務
申請代行業務の概要を知ることは、依頼する社労士を選考するためには重要なことす。
ここでは、現在最もポピュラーなキャリアアップ助成金の正社員化コースを例にとって助成金申請代行の業務を検証してみましょう。
代行業務は、大凡次のようなものからなります。
① キャリアアップ助成金の受給要件等の概要を事業主に説明する。
② キャリアアップ計画書を作成して、労働局に提出・説明する。
③ 就業規則を修正し、労働基準監督署に届け出る(就業規則がないときは、新規に作成)。
④ 雇用契約書(有期契約時及び正社員に転換時)を作成又は手直しする。
⑤ 1年間にわたり、毎月の労働時間の集計、賃金計算、法定帳簿の作成を指導又は代行する。
⑥ 助成金の請求書を作成して、労働局に提出・説明する。
⑦ 労働局からの問い合わせに説明・回答する。
これだけの業務があります。
3 助成金社労士選考の視点
① 助成金に積極的に取り組んでいる社労士(助成金に熱心でない社労士には注意)
② 助成金のうま味だけでなく、リスクについても説明してくれる社労士
③ 助成金の受給まで何度もコンタクトしてくれる社労士
④ 労働時間の集計や給与計算など自社で十分な対応ができないことは、根気よく説明あるいは代行してくれる社労士
※ 労働時間の集計や給与計算を甘く見てはいけません。これが正しくできないかぎり、助成金は受給できないと思ってください。
⑤ 可能ならば顧問契約の締結を考慮すること
・ 報酬の高い安いのみを判断基準としないこと(事業主としては、実際に受給できるかどうかが最も重要)
・ 顧問契約を締結する場合、社労士と接触する機会が多く、受給ミス(もらい損ね)を最小に抑えることができる。
Ⅳ 就業規則を依頼する社労士の選び方
あなたは就業規則専門の社労士を探しますか?
そうではありません。
労働問題全般を担当する社労士の中から、
就業規則が得意、又は あなたの重視する分野が得意 とする社労士を探しましょう。
※ 企業支援(労務管理)を専門とする社労士なら、多くの社労士は就業規則を作成するでしょう。
そう就業規則の作成をしない社労士は、ほとんどいないと思われます。
1 就業規則を作成・変更する場合の契約
就業規則を作成する場合、どのような契約を締結しますか。
通常は就業規則の作成・変更に契約内容を限定して、スポット契約を結びます。
既に顧問契約を締結している場合も同じです。
ただし、ごく稀に就業規則の見直しまで含んだ顧問契約を結んでいるケースがあります。
その場合は、顧問契約の範囲内業務として取り扱われます。
2 就業規則を依頼する社労士探しの視点
(1)一般的な就業規則を作成する場合
小さな会社の場合、特別なこだわりのない一般的な就業規則を作ることが多いようです。
就業規則は労働法に基づいて作るものであり、
他社とは違う完全にオリジナルな就業規則というものはありません。
どこの社労士でも貴社の実情に合わせてカスタマイズはしてくれます。
難しく考えないで、次のような社労士さんを選ぶといいでしょう。
① 労務管理については、何でもやる社労士
就業規則は、労務管理の基盤となる大切なもの
労務管理ならば何でもできるという人でなければ、まっとうな就業規則は作れません。
※「就業規則は得意だが、労働時間や賃金の管理に関することは不得手」などという社労士では困ります。
換言すれば、労務管理や労働・社会保険については「何でも屋」でなければなりません。
② 自分の求める能力・性格の社労士
事前の話し合いの中で、自分に合う人か合わない人か、
また自社に合う規則・制度を作ってくれそうな人かよく確認してください。
(2)こだわりのある就業規則を作成する場合
小さな会社でこのようなことはあまりないと思われますが、
会社の事情に良く適合したこだわりのある就業規則を作る場合は,
次のような視点で選ぶといいでしょう。
① 就業規則の作成を得意分野とし、十分な実績を持つ社労士
② できれば、貴社の業界に特化して活動している社労士
例;建設業専門、介護業界専門、飲食業専門etc.
③ 労務管理の特定分野にこだわりがある場合は、その特定分野の業務を得意としている社労士
※ 特定分野へのこだわり(例)とは;
“社内規律を刷新したい”“労働時間制度を革新したい”残業時間を削減したい“”“オリジナルな評価・賃金制度を構築したい”など
Ⅴ 社労士の専門性について
企業が社会保険労務士を選ぶ場合、専門分野を持つ社労士と持たない社労士どちらがいいと思いますか?
やはり“社労士の専門性”について、知識が必要ですね。
以下、社労士の専門性について私見を述べます。
社労士には、大きく分けて“年金問題を専門とする社労士”と“企業の労務管理等を専門とする社労士”に大別できましょう。
1 年金問題を専門とする社労士
主として年金加入者たる個人に対し、年金問題に係るカウンセリングや手続きを専門又は得意分野とする社労士です。
年金を専門とする社労士には、年金のみに特化する社労士と、年金と企業の労務管理の両方を行う社労士がいます。
年金のみに特化する社労士は、通常、企業の労務管理にはタッチしていないようです。
企業にとっては、次項に説明する労務管理等を専門とする社労士の必要性が高く、年金を専門とする社労士の必要性は特定の場合を除いて小さいといえましょう。
2 労務管理や労働・社会保険を専門とする社労士
企業にとって必要性の高い社労士で、一般に企業に出入りする社労士の多くはこのタイプです。
年金問題についても、企業経営に必要な分野は守備範囲です。
ただし、この中にはいくつかのパターンがあって「業界特化型社労士」「特定業務特化型社労士」「(特定の業界や業務に特化しない)何でも屋社労士」がいます。以下これらについて簡単にご説明します。
① 業界特化型社労士
建設業界専門、介護業界専門、飲食業界専門などと、いうように得意とする業界を持つ社労士です。
このような肩書を持つ社労士は、少なくともその業界についてはある程度以上に詳しいでしょうから、もし見つかれば業界特化型社労士を選ぶのもよろしいでしょう。
ただし、業界特化型の社労士はそんなに多くはないのかもしれません。
また、本当にその業界に詳しいかどうかは、面接等を通じて確認してください。
② 業務特化型社労士
「就業規則専門」「賃金管理専門」「人事労務管理専門」「助成金専門」などといった社労士です。
このような肩書を持つ社労士は、少なくともその業務についてはある程度以上に詳しいでしょうから、特定の業務に注力してもらいたいときは業務特化型社労士を選ぶのもよろしいでしょう。
ただし、業務特化型社労士の中には、なんでも屋社労士と変わらないくらい専門分野をたくさん持っていたり、特に専門分野に特化しているわけでもないのに、「○○専門」とうたった方がお客さんをとり易いからといった理由で「○○専門」と称していることも少なくないと思われます。注意が必要です。
※ 本当に例えば就業規則を専門とする社労士が居たとします。この社労士が、就業規則を作るに際し「服務規律の指導は苦手です」あるいは「賃金については、あまり詳しくありません」などということがありうるでしょうか。そのような社労士がチャンとした就業規則を作れるとも思えません。
ただし、少なくとも専門分野には自信があると思われますので、特定分野にこだわりのある仕事を依頼する場合などは、業務特化型社労士を選ぶのもよろしいかと思われます。
その意味では、「人事制度や賃金制度専門」「助成金専門」といった社労士は使いやすいのかもしれません。
③ 何でも屋社労士
労務管理や労働・社会保険など企業に必要な業務なら何でもやるというタイプの社労士で、最も多いタイプの社労士です。
企業は労務管理や労働・社会保険全般の補佐を求めているのですから、原則的には「労働問題なら何でも屋社労士」なければならないはずです。
ただし、「何でも屋社労士」にも人事・賃金制度や助成金など特定分野はやらない社労士や逆に特定の分野(例えば手続き業務のみ)しかやらない社労士も居ますのでよく見極めてください。
お問合せ・ご相談はこちら
お電話でのお問い合わせ.ご相談はこちら
048-783-7888
info@rohmkanri.jp
担当:楠瀬(くすのせ)
受付時間:9:00~1700
定休日:土日祝日
主として従業員30人以下の中小企業を支援する埼玉の社会保険労務士
“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)
労働時間や賃金の管理、問題社員への対応、労働・社会保険の手続き・管理、行政への対応など、小さな会社を懇切丁寧に支援します。
助成金の申請もお任せください。
対応エリア さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市などを中心に埼玉県内各地
無料相談実施中
サイドメニュー
人事・労務全般
労働時間・休暇等
賃金管理
労使トラブル
助成金申請
労働・社会保険
その他の記事
無料相談・お問合せ等
楠瀬労務管理オフィス
住所
〒331-0825
埼玉県さいたま市北区
櫛引町2-509-42
アクセス
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日
各種簡易診断
実施中(無料)!

主な業務地域
大宮、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市を中心に埼玉県全域


